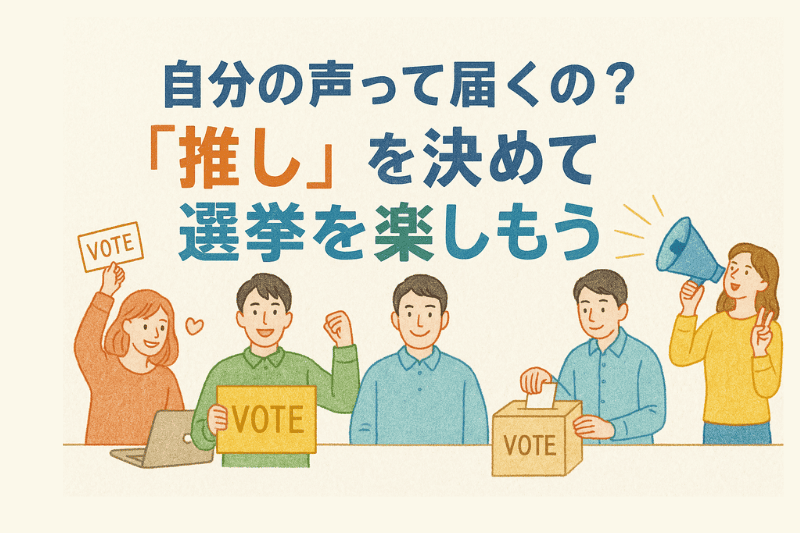
「どうせ選挙に行っても何も変わらない」──そんなイメージ、ありませんか?
でも、好きなアイドルやキャラクターを応援する“推し活”のように、自分が応援したい候補者や政党を見つけると、選挙がぐっと身近で楽しいものに変わってきます。
この記事では、
- 候補者の選び方や応援の仕方
- 選挙カーの意味や運動の裏側
- 議員の役割
など、選挙を身近に感じるヒントを紹介しています。
「社会を変えたい!」じゃなくても大丈夫。
「今の暮らし、ちょっと良くなればいいな」──そんな気持ちからでも、未来を動かす力になります。
 さかぽん
さかぽん私自身、政治の知識はまだまだ。だからこそ、間違っていることがあれば遠慮なく教えてもらえると助かります。
選挙がもっと身近になる“推し活”という視点
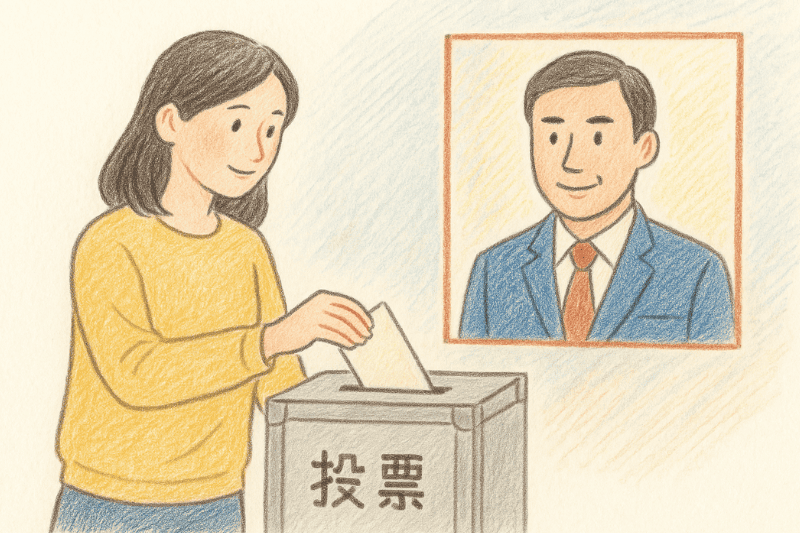
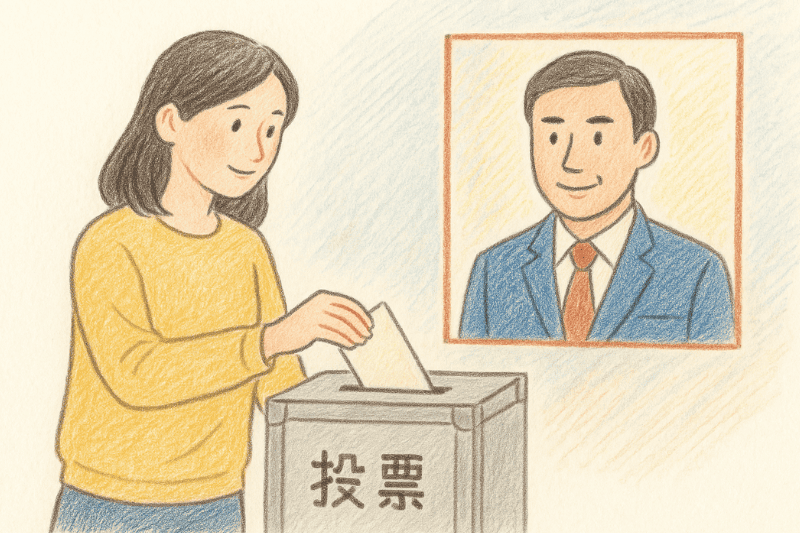
選挙は難しいものではありません。投票は名前を書く数分で終わります。
でも、そこに向けて「誰(政党)に託すか」を探す過程は、まさに“推し”探し。
「この人になら任せたい」と思える候補者が見つかると、選挙結果にもハラハラ・ドキドキするはず。
候補者の選び方|3つの視点でチェック


「人気(知名度)」や「なんとなく好きだから」ではなく、その人や政党の公約が、自分にとって本当にプラスになるか?を考えて選びたいところ。
1.公約で絞る
自分の暮らしを守るために、実現してほしい政策を掲げている人(政党)から探してみましょう。
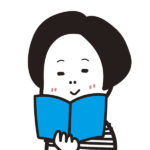
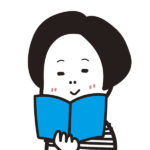
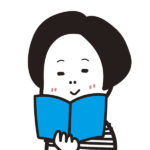
ただし、有権者が望むことを”言うだけ”ならなんとでも言えるもの。
その政策が本当に実現できそうか、実行力やこれまでの実績もチェックしてみて。
2.投票マッチングサービスを活用
選挙が近くなると、NHKや新聞社、選挙サイトなどで「ボートマッチ」「投票マッチング」といったコンテンツが登場します。
あなたの考えに近い立候補者や政党がわかるので、判断材料のひとつとしておすすめです。
3.活動内容から「想い」に共感できるか
WebサイトやSNS、時には実際に会って感じた”温度感”も大切な要素です。
選挙前には地域で「立候補者による討論会」も開催されることがあり、その様子がWebで配信されることも。
言葉や表情の一つひとつから、考えの深さや人柄が伝わってくるので、判断のヒントになります。



バレたくないことがあって、討論会に出ない人も…これも判断材料!
参議院選挙の比例代表は「個人名」優先で
参議院選挙では「選挙区」と「比例代表」の2つの選挙があります
つまり、政党名よりも「個人名での得票数」が当落に大きく関わるのです。
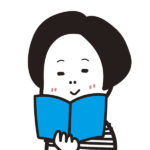
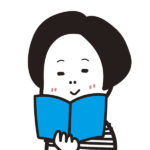
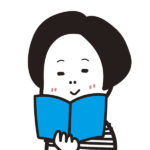
応援したい人がいる場合は、その人の名前を書くのが、一番確実な応援方法です。
なお、一部の候補者は、政党が優先して当選させたい「特定枠」に入っていて、個人名での得票がなくても当選しますが、多くの候補者は得票数順で当落が決まります。
まだ「国政政党」でない政党の場合、選挙区もしくは比例のどちらかで、有効投票数の2%以上を獲得し、国会議員が1人以上いれば国政政党の要件を満たせます。
そのため、選挙区で落選しそうな候補者でも、その1票が政党にとって大きな意味を持つケースもあります💪
わかりやすい解説動画
それでも「推し」が見つからないときは?
「この人(政党)だけには任せたくない」という気持ちも、立派な選択理由です。
たとえば、「この候補が当選すると困る」と感じるなら、その人に票が集まらないように、他の候補に投票するという選び方もあります。
これは「戦略的投票」と呼ばれることもあり、より自分にとって悪影響が少ない選択肢を選ぶという考え方です。
選挙特番では「落選」が大きく取り上げられることも多く、「よっしゃ落ちたー!ビールがうまい」なんて楽しみ方をしている人もいるようです(笑)


選挙を“推し活”のように捉えるのが難しいと感じたときは、そんな視点でもOK。「投票しないより、なんらかの意思表示をすること」が大切なのです!
投票日に気をつけたいこと


投票日当日は、知らずにうっかりやってしまいそうな行動も「選挙運動」とみなされ、禁止されています。
公職選挙法で定められており、違反すると罰則が科される可能性もあるため注意が必要です。
たとえば、こんな行為はNG
- 特定の候補者や政党への投票に影響を与えるような発言(当選または落選に関わる内容)
- SNSで特定の候補者や政党に関する投稿をRT(リツイート)やシェアすること
- 「〇〇さんを応援してます!」といったコメントやタグ投稿もアウトです
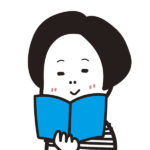
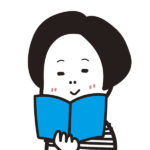
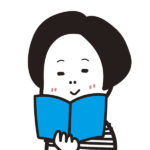
一方で、「投票に行こう!」と呼びかけること自体は問題ありません。
SNSは気軽に投稿できる分、選挙当日にうっかり違反してしまう人も少なくありません。
応援する気持ちがあるからこそ、“推しの人”に迷惑をかけてしまわないよう、公職選挙法には十分気をつけましょう。
違いを認め合える“推し活”を



“自分の推しの人”を否定されたら、傷つく気持ちになりますよね。
それは、他の人にとっても同じです。自分の応援を伝える際には、「自分の推し以外を否定するような発言」は控えるようにしたいものです。
政治の話はなんとなくタブーとされがちですが、本来は、私たちの暮らしに直結する身近な話題です。
大切なのは、誰かに考えを押しつけることではなく、「自分の暮らしをより良くするには、どんな社会がいいんだろう?」と考えること。
そんな前向きな視点をこころがければ、自然と会話もしやすくなるかもしれません
投票した後も大事!候補者の活動をチェックしよう
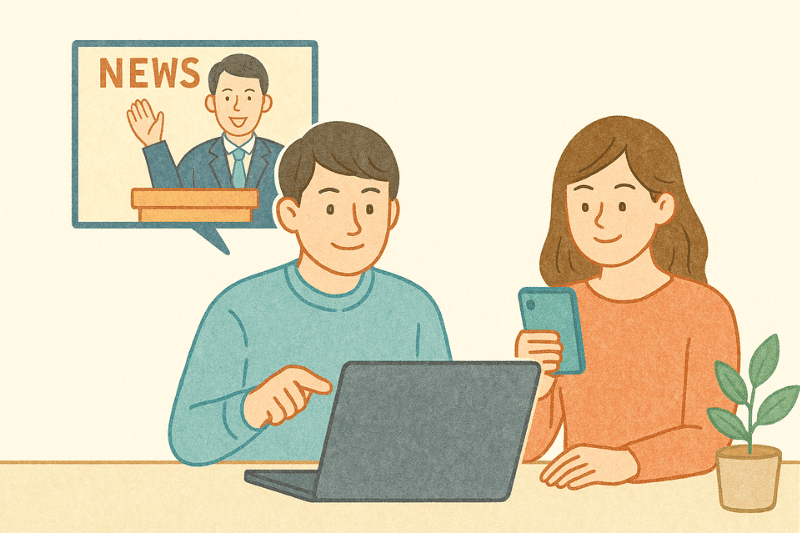
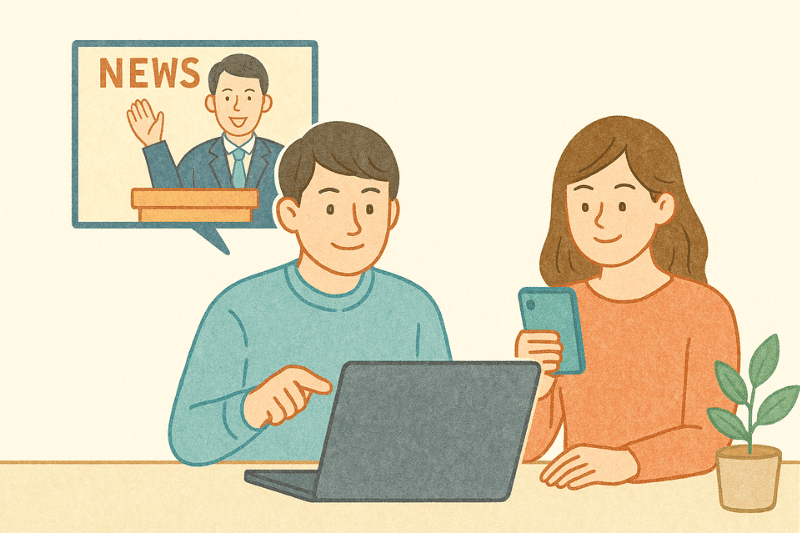
「投票したら終わり」ではないのが選挙の面白さ。むしろ、当選したあとにどう活動してくれるかを見守ることこそが、私たちにできる応援のカタチかもしれません。
たとえば、各自治体や国の議会サイトでは、次のような情報が公開されています。
- 質問内容や発言記録
- 陳情・請願の内容と対応
- 意見書・決議の内容
実際にチェックしてみると、日々の暮らしや仕事にも関わるような内容ばかりで、意外と身近に感じられるはずです。
選挙運動のリアル|なぜあんなに声を出して走るの?


立候補者たちがどんな毎日を過ごしているか、知っていますか?
想像以上に過酷な日々のなかで、それでも諦めずに走り続けている姿を知ると、自然と応援したくなる気持ちが湧いてきます。
ここでは、実際に関わった体験を交えながら、選挙運動のリアルな姿をお届けします。
選挙カーはなぜ走る?うるさいけど必要な理由
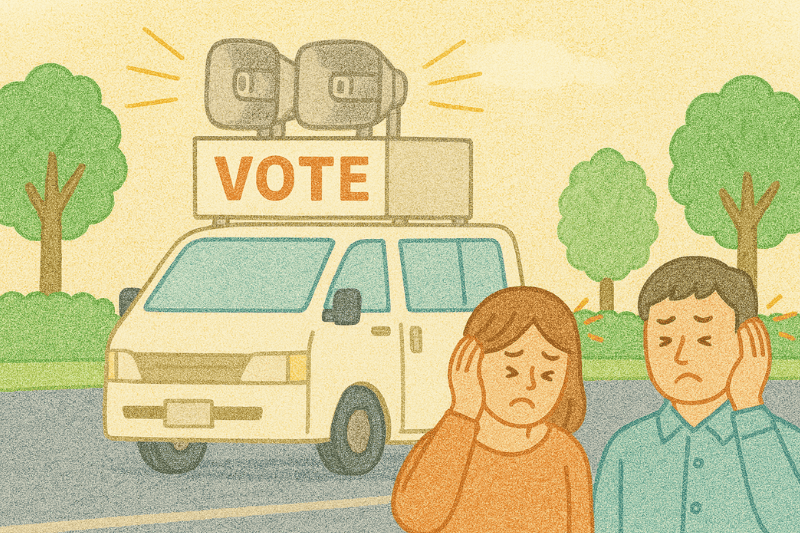
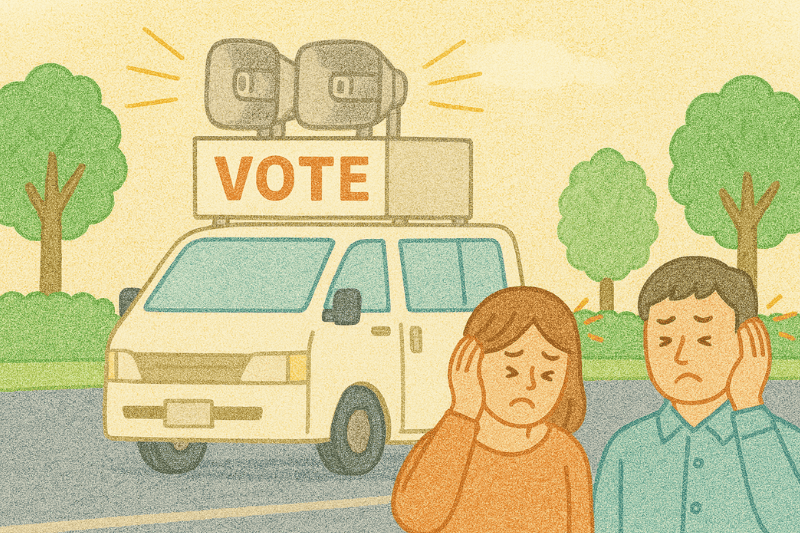
「選挙カー=うるさい」という印象を持つ方も多いかもしれません。でも実は、日本の選挙制度における大切な仕組みのひとつ。背景を知ると、見え方が変わるかもしれません。
日本の選挙は「やってはいけない」ことばかり。「べからず集」と呼ばれるほど、細かく制限されています。ポスターや看板のサイズ、掲示場所など細かなルールがたくさん。
なかでも特徴的なのが「戸別訪問の禁止」。欧米ではよくある、1軒1軒まわって対話するスタイルは、日本では資金力の差による不公平を避けるため、法律で禁止されているのです。
その代わりに認められているのが「選挙カー」。
候補者の名前を繰り返し伝え、できるだけ多くの人に知ってもらう──限られたルールのなかで、候補者が存在を知らせるための手段なのです。
【豆知識】選挙運動期間中は午前8時から午後8時まで、選挙カーでの連呼行為(氏名などの繰り返し)が認められています(公職選挙法第140条の2第1項の規定)
選挙運動は1日12時間以上の激務!体力勝負の毎日
選挙運動期間は、選挙の種類によって異なります。
| 参議院議員選挙 | 17日間 |
| 都道府県知事選挙 | 17日間 |
| 衆議院議員選挙 | 12日間 |
| 都道府県議会議員選挙 | 9日間 |
| 一般市 市長選挙 | 7日間 |
| 一般市 市議会議員選挙 | 7日間 |
| 町村長選挙 | 5日間 |
| 町村議会議員選挙 | 5日間 |
もちろん、候補者には“休み”はありません。
活動時間の8:00〜20:00だけでなく、その前後の準備や片付け、翌日の計画も含めるとまさに“超多忙”。
体力・気力を削りながらも、「ひとりでも多くの有権者に想いを届けたい」という気持ちで動き続けています。
私がウグイス嬢として携わったのは、合間に休みをいれながら6日間だけでしたが、お手振りで筋肉痛・声出しで喉が枯れ・座りっぱなしで腰が痛くなる毎日。
選挙終了後には一気に疲れが出て、しばらく体調を崩しました…。
立候補者はそれを最大17日間、休みなく続けているのです。
最終日が近づく頃には喉も限界。それでも必死に走り続ける姿に、大変さを知った今では、自然と応援したい気持ちが生まれました。
「うるさいだけ?」と思っていた私が変わった理由
私は最初「選挙カーって、うるさいだけじゃない?」と思っていました。
でも、実際にウグイス嬢として選挙カーに乗ってみて驚いたのは、信号待ちのたびにたくさんの人が笑顔で手を振ってくれること。
中学生の集団や小さな子どもたちまでもが、「がんばれー!」と声をかけてくれる──それは予想もしなかった温かさでした。
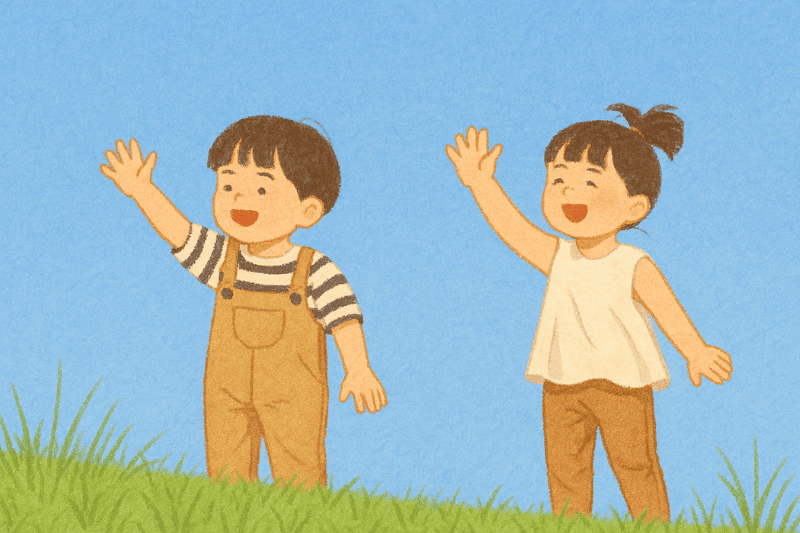
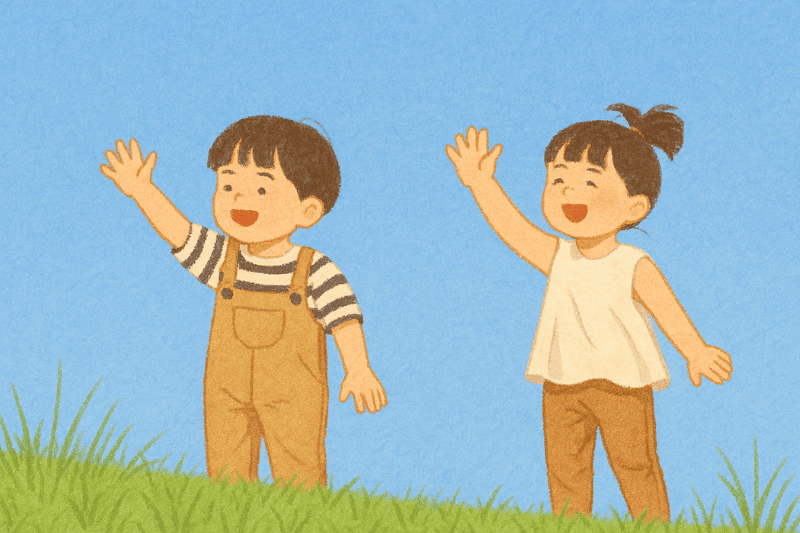
手を振ると、立候補者は全力で応えてくれる。そのやりとりが楽しくて、面白くて、うれしい。
まるでイベントのように、みんなが笑顔になっていく。選挙カーのまわりには、そんなコミュニケーションの連鎖が広がっていました。
印象的だったのが、「この目でどんな人か確かめたい」と、到着を待ってくれている方々の存在です。
「会いたくて待っていた」と話しかけてくれる人たちからは、「自分にはできないからこそ、代わりに頑張ってくれる人に託したい」という想いがひしひしと伝わってきました。



地域に足を運んで、ちゃんと向き合おうとしてくれる人──
そんな“熱意ある人”を選びたい、という声もあるんです。
選挙運動はまさにマラソンのよう。沿道から「がんばれー!」と手を叩いて応援してくれる人たちがいて、その声が、走り続ける立候補者の大きな支えになっていました。
最初は正直なところ意識が低かった私。けれど、どんなに疲れていても応援に反応して、目を潤ませている立候補者の姿を間近で見てからは、私自身の意識がガラッと変わりました。
立候補者のためだけでなく、応援してくれている人のためにも“応援のサインを見逃さない”という真剣な気持ちになったんです。



応援のサインを見つけたら、すぐに候補者に伝える。ひとつひとつの声に、応えるために。
政治家って、なんとなく“遠い存在”のように思われがちかもしれません。
でも実際は、私たちと同じ社会で生きている、一人の人間。いろんな想いを抱えながら、勇気をもって立ち上がっています。
「どんな批判も受けとめる」と覚悟を決めていても、もちろん凹むこともあるし、何気ない一言や行動が、思わぬ大きな批判につながることも。
だからこそ、街のなかで交わされる一言、手を振るしぐさ──
そうした「自分のことを信じてくれる人がいる」と感じられる応援は、心にぐっと響いて、背中を押す大きな力になっていると、私は実感しました。
復習!市町村議会・県議会・国会(衆議院・参議院)の違い
それぞれの議会には「地域の課題をどうするか」「社会をどう良くしていくか」を考える大切な役割があります。
次の選挙に向けて、「誰が何を考え、どんな行動をしてきたか」に注目してみると、見え方が変わってくるかもしれません
議員って、報酬がムダに高い?
そんなふうに感じてしまうのは、きっと「何をしているのか」が見えにくいから。
でも実際には、議員たちは日々さまざまな業務に取り組んでいます。
- 問題解決のための勉強会に参加
- 課題の調査・研究(時には専門家の力を借り調査費も必要)
- 議会に向けた資料づくりや準備
- 協力を得るための人間関係づくり、調整
さらに、こうした活動を円滑に進めるためには、秘書などのサポート人材の人件費も必要とされます。
真剣に課題と向き合えば向き合うほど、時間もお金もかかるのが現実です。
一方で、日頃の活動が見えづらかったり、「なんでこれに?」と思うような費用が使われていると、「ムダに高い」と感じる人がいるのも自然なこと。
そうした声の背景には、“本当に想いをもって議員になったの?何か別の目的があるのでは…”という不信感があるのかもしれません。



ムダじゃないって思える人が、ちゃんと当選できるように応援したいよね!
立候補するにはお金がかかる?供託金とは
選挙に立候補するには「供託金」が必要です。これは、軽い気持ちでの立候補や売名行為を防ぐためのしくみ。
一定の得票数に届かなかった場合、供託金は没収され、公的な目的に使われます。
主な供託金の額と没収ライン(一部抜粋):
| 選挙区 | 供託金 | 没収点 |
|---|---|---|
| 衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効投票総数×10分の1未満 |
| 参議院 選挙区 | 300万円 | 有効投票総数÷定数×8分の1未満 |
| 都道府県知事 | 300万円の1 | 有効投票総数の10分の1未満 |
| 都道府県議会 | 60万円 | 有効投票総数÷定数×10分の1未満 |
市町村議会:もっとも身近な議員たち
市町村議会では、その市や町の「条例の制定・改正」や「予算の決定」などが話し合われます。たとえば「ごみの分別ルール」や「子育て支援の助成金」など、暮らしに直結する内容も少なくありません。
議員たちは、市(町村)長の方針や提案についてもしっかりと議論し、物事が適切に進んでいるかもチェック。
また、地域の集会やお祭りなどにも積極的に参加し、住民との関係性を築きながら声を集め、課題の解決策を考えて実践していく。まさに、いちばん身近な存在です。
| 任期 | 4年 |
| 被選挙権 (立候補の権利) | 満25歳以上で、その市町村議会議員の選挙権を持っている人 |
県議会:市よりも広い視点で県全体を見つめる役割
県議会も、「条例の制定や改正」「予算の決定」などを行なっています。たとえば「高校の統廃合」や「医療機関の再編」など、県全体に関わる身近な話題も多くあります。
議員たちは知事の方針や政策についても議論し、実施状況をチェックします。
ただし、スケールが広いため市議会よりも活動が見えにくい面も。その分、「タウンミーティング」など、県民と直接話す場を設けるなどの工夫をしているケースもあります。
| 任期 | 4年 |
| 被選挙権 (立候補の権利) | 満25歳以上で、その県議会議員の選挙権を持っている人 |
国会(衆議院・参議院):『国』の法律や予算について決定
日本の国会は「衆議院」と「参議院」からなる二院制です。
衆議院は解散があるため任期が短く、国民の声(世論)をより反映しやすいとされています。
そのため、両院で意見が異なった場合には「衆議院の意見が優先される」(衆議院の優越)というルールがあります。
| 衆議院 | 参議院 | |
|---|---|---|
| 議員定数 | 475名 | 242名 |
| 任期 | 4年 | 6年 (3年ごとに半数を改選) |
| 被選挙権 (立候補の権利) | 満25歳以上 | 満30歳以上 |
| 解散 | あり | なし |
まとめ|“応援したい”気持ちが、未来を変える


・国民が政治を嘲笑しているあいだは嘲笑い値する政治しか行なわれない。
国民はみずからの程度に応じた政治しかもちえない――松下幸之助の政治観(4) | 松下幸之助.com
・民主主義国家においては、国民はその程度に応じた政府しかもちえない。
「政治に関心がない」のではなく、どう関わればいいのか、わからなかっただけかもしれません。
でも、「関心を持つこと」や「応援すること」が、誰かの背中をそっと押す力になることも。
そうやって志ある人が立ち上がりやすい空気が広がっていけば、社会も少しずつ前向きに変わっていくと信じています。



推し活みたいに、自分なりの視点で“応援したい人”を見つける。
それが選挙を楽しむ、第一歩かもしれません。


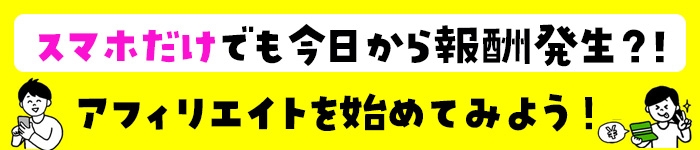

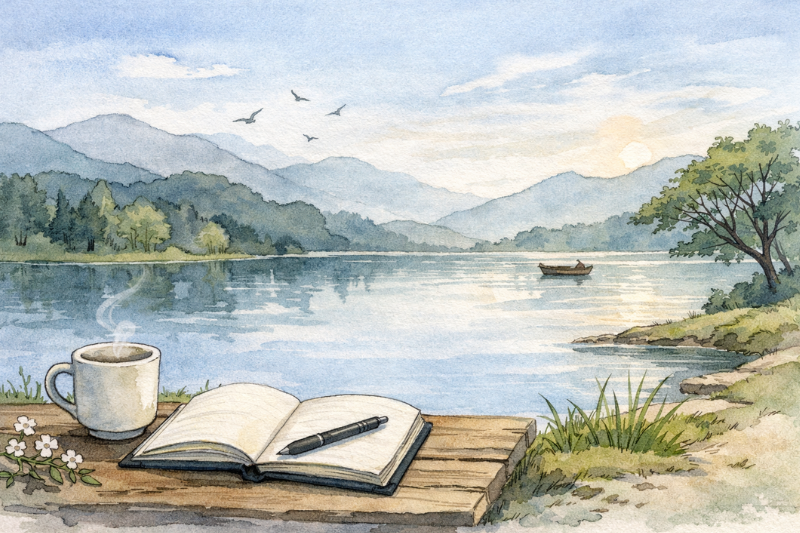

コメント